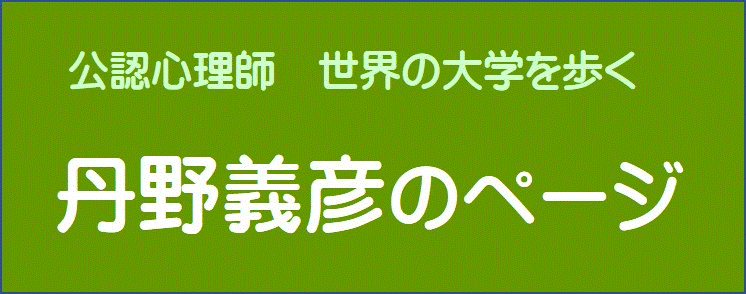2016世界行動療法認知療法会議(WCBCT)メルボルン 2016年6月 丹野義彦
2016年6月にオーストラリアのメルボルンで開かれた世界行動療法認知療法会議(WCBCT2016)に参加した。日本からも多くの人が参加した。
1.どんな学会が、いつ、どこで開かれるか。
学会:世界行動療法認知療法会議(World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies: WCBCT)
会期:2016年6月22日~25日
会場:オーストラリア メルボルン
メルボルン・コンベンション・エキシビション・センター
2.どんな領域の研究者が参加するか、どんな雰囲気の学会か。
WCBCTは、3年に1回開かれる行動療法・認知療法の国際学会である。
1979年から開かれてきた世界行動療法会議と、1983年から開かれてきた国際認知療法学会とが合体した学会である。
第1回は1995年にコペンハーゲン(デンマーク)で開かれた。
第2回は1998年にアカプルコ(メキシコ)で開かれた。
第3回は2001年にバンクーバー(カナダ)で開かれた。
第4回は2004年に神戸(日本)で開かれた。アジアで初めて開かれたWCBCTであり、この大会をきっかけとして、日本に認知行動療法が本格的に普及した。日本にとってエポックメイキングな大会であった。
第5回は2007年にバルセロナ(スペイン)で開かれた。
第6回は2010年にボストン(アメリカ)で開かれた。
第7回は2013年にリマ(ペルー)で開かれた。
第8回が今回で、2016年にメルボルン(オーストラリア)で開かれたものである。
今回の大会テーマは「認知行動療法の世界的発展と革新Advances and innovations in the behavioural and cognitive therapies across the world」というものである。
同時に19会場が並列しておこなわれた。
3.学会の規模はどれくらいか。 何人くらい参加するか。
この大会には、世界40カ国からの参加があった。認知行動療法が世界的に定着しつつあることを示している。日本も例外ではなく、日本からは100人以上が参加した。これだけ多くの日本人が大挙して参加する海外の学会は珍しい。
・ワークショップは、27本である。
・講演は、44本である。
・シンポジウムは、131本である。
・口頭発表のセッションは54コマ(約200本)おこなわれた。
・ポスター発表は、254本である。
今回の大会と、過去4回の大会のプログラムを比較してみよう。講演数と口頭発表のセッションはこれまでで最も多かった。ワークショップとポスター発数がこれまでよりも少なめであるが、シンポジウムはほぼ同じである。
|
|
2001 バンクーバー |
2004 神戸 |
2007 バルセロナ |
2010 ボストン |
2016 メルボルン |
|
ワークショップ |
34本 |
31本 |
86本 |
71本 |
27本 |
|
キーノート講演 |
3本 |
4本 |
- |
34本 |
|
|
招待講演 |
11本 |
21本 |
39本 |
|
44本 |
|
ワールドラウンド |
12本 |
5本 |
- |
|
|
|
ランチョンセミナー |
- |
8本 |
- |
|
|
|
教育セッション |
- |
3コマ |
- |
|
|
|
シンポジウム |
101本 |
31本 |
182本 |
136本 |
131本 |
|
口頭発表セッション |
0本 |
14コマ |
51コマ |
30コマ |
54コマ |
|
ポスター発表数 |
363本 |
200本 |
890本 |
860本 |
254本 |
|
公開講座 |
- |
1コマ |
- |
|
|
|
参加者 |
2470名 |
1400名 |
4000名 |
2300名 |
? |
4.どんなプログラムがあるか、その内容で印象に残ったことは
1)開会式
初日の夕方にはオープニング・セレモニーがおこなわれた。場所は会場のプレナリーAである。
開会式はアボリジーニの音楽と少女の踊りから始まった。
続いて、大会主催者のロス・メンジーズ(シドニー大学)の挨拶があった。
最後にデイビッド・クラーク(オクスフォード大学)が、「認知行動療法:過去・現在・未来」というタイトルのオープニング講演をおこなった。
開会式では、坂野雄二先生、大野裕先生、イギリスのサルコフスキス先生などと会った。
開会式が終わると、レセプションがあり、オーストラリア・ワインビールなどが無料で配られた(参加費に含まれていた)。
2)アーロン・ベックのビデオ講演
6月23日朝8:30から、アーロン・ベックのビデオ講演とパネル・ディスカッションがあった。朝早かったが、広い会場はほぼ満員となった。
アーロン・ベックは95歳になった。今でも元気に仕事しているという。娘のジュディスと一緒に出ていた。最後に、ベックの誕生日を祝って拍手した。
ベックから、パネルディスカッションのために、4つの質問が出た。
3)パネル・ディスカッション
ベックからの4つの質問に答える形で、ディスカッションがおこなわれた。
デイスカッサントはクラーク、サルコフスキス、ジュディス・ベックらである。4つの質問とは以下である。
Question 1
精神病の陰性症状へのCBTについて
Question 2
多くの障害にどう広げていくか? パーソナリティ障害、自殺、摂食障害、精神病・・
Question 3
IAPTやベック・イニシアチブのように地域に広げるにはどうしたらよいか?
IAPTは認知行動療法の普及に革命的な影響を与えた。その中心で仕事をしたクラークは、認知行動療法の英雄のように扱われていた。
Question 4
治療同盟について。認知行動療法は、治療プロセスよりも、治療効果に焦点が当てられてきた。これについてどうか?
4)キーノート講演
6月24日には、クラークによるIAPTについてのキーノート講演があった。彼らが出版した" Thrive"の紹介があった。私はちょうどこの本を翻訳している時だったので、大いに理解が深まった。重要だったのは、心理学者によるロビー活動と、政治家からのサポート(労働党政権のブレア、ブラウン、ジョンソン、保守党政権のキャメロン、フレッグなど)であると言っていた。
5.日本から誰が参加していたか。
この大会では、日本人が多く参加していた。認知行動療法関係の国際学会の常連である坂野雄二先生と大野裕先生とは今回もいっしょになった。丹野も含めて、この三人は認知行動療法業界の「3野」と呼んでいる。
また、若い大学院生が多く参加していた。大学院生が国際学会で英語で発表するのは当り前という雰囲気になったのはうれしい。国際学会に参加するのは、若ければ若いほど刺激があるので、たいへん望ましい。
大学院生が多く参加できた原因として、日本認知療法学会による若手研究奨励基金と、日本認知・行動療法学会による発表助成金といった経済的後押しがある。
6.次回の学会はいつどこで開かれるか。
次回のWCBCTは、2019年にドイツのベルリンで開かれる。
場所:ベルリン CityCube Berlin (CCB)
日時:2017年7月17日~20日
公式ホームページ http://www.wcbct2019.org/